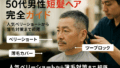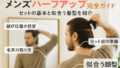「顎を引いた瞬間、写真に映る自分の“二重顎”が気になった経験はありませんか?実は日本人女性の約60%が、顎まわりの悩みとして『二重顎』を挙げています。体型に関係なく、骨格や筋肉、姿勢といったさまざまな要素が複雑に絡み合い、“痩せているのになぜ?”と戸惑う方も少なくありません。
特にスマートフォン・PCの普及以降、猫背やストレートネックの割合は急増。日常の何気ない姿勢やクセが、知らぬ間にフェイスラインのたるみを助長し、年齢を問わず二重顎リスクを押し上げています。また、最新医学データでも、顔や首の筋肉の衰えは30代から加速しやすいことが示唆されています。
「どうすれば改善できる?そもそも自分の原因は何?」と不安や疑問を感じていませんか?このページでは、専門家による医療データと具体的なセルフチェックの方法をもとに、誰でも実践できる解決策を徹底解説。最後まで読めば、“その場しのぎ”ではない根本対策や、日常のちょっとした工夫で小顔が叶うメソッドまで知ることができます。
二重顎を放置すれば、将来的な健康や外見への悪影響も…。今こそ原因から正体を知り、明日からの笑顔に自信を取り戻しましょう。
顎を引くと二重顎になる本当の理由を徹底解説
顎を引く動作とフェイスラインの変化の仕組み
顎を引くと二重顎が目立つ理由は、下あご下部から首にかけての皮膚や脂肪が圧縮されることで、たるみやもたつきが強調されるためです。普段から顎周りの筋肉を使わないと、筋肉が衰えて皮膚の弾力も落ちやすくなります。特に生活習慣や加齢、表情筋の活動低下が影響します。さらに筋肉の緊張と弛緩のバランスが崩れると、リンパや血流が悪化しむくみが増しやすくなります。
以下のポイントに注意すると良いでしょう。
- 姿勢の悪化や首まわりの筋力低下も要因
- 皮膚のたるみ・脂肪の蓄積に注意
- 柔軟な筋肉を保つ表情運動が効果的
このメカニズムを理解し、適度な筋肉の緊張を保つ生活習慣を意識することがフェイスラインを美しく保つコツです。
顎を引く癖とストレートネック・骨格の深い関係性
ストレートネックや猫背などの姿勢の崩れは、顎を引く際に首や顎下の皮膚や筋肉への負荷を高めます。現代ではスマホやパソコンの長時間利用が定着し、自然と前傾姿勢や「うつむき癖」が身についている人が多いです。首の筋肉が正しく使われなくなると、フェイスラインが乱れやすくなり、二重顎が強調されます。
テーブル
| 姿勢習慣 | 二重顎リスク |
|---|---|
| スマホ首 | 高い |
| 猫背 | 高い |
| 机に顔を近づける | 高い |
| 顎を突き出す癖 | 中程度 |
首や肩のストレッチ、姿勢矯正トレーニングを日常に取り入れることで、余計な負担を減らし、美しい輪郭を維持しやすくなります。
痩せ型でも二重顎になる科学的背景と誤解の訂正
「痩せているから二重顎にならない」という思い込みは誤りです。骨格が小さい人や下顎の発達が少ない場合、皮膚や脂肪がたるみやすく、二重顎が目立ちやすくなります。また、顔や首まわりの筋肉が弱い人もたるみやすいです。
- 骨格の小ささ → 顎下に脂肪や皮膚が集まる
- 筋肉不足 → フェイスラインの引き締め力低下
- 遺伝的な骨格・加齢も要素
このため、痩せ型の方も顔・首の筋トレや日々の表情運動、バランスの良い食生活で筋肉量を維持することが重要です。
写真撮影時の「顎を引く」が二重顎を目立たせる理由と対策
証明写真や自撮りの際、顎を引きすぎると首にしわやたるみができやすく、二重顎がより顕著に写ります。心理的に「真っ直ぐ撮らなければ」「小顔に見せたい」という意識も過度な顎引きを招きやすいです。
写真を撮る際の対策
- 顎を軽く引き、背筋はしっかり伸ばす
- 舌を上顎につけて首元の筋肉を自然に引き上げる意識を
- リラックスした状態で口角を上げる表情を心がける
- 首をまっすぐに伸ばして正面を向く
小顔効果を演出する表情・ポージングの科学
- 首筋を伸ばし、軽く前に突き出すことでフェイスラインがシャープに見える
- 舌を上顎に沿わせることで顎下の筋肉が適度に緊張し、たるみを抑制
- 軽く微笑むことでフェイスラインが引き上がる効果
写真撮影や普段の姿勢にこれらの動きを意識的に取り入れることで、二重顎を目立ちにくくし、美しい小顔を演出できます。
二重顎ができる主な原因と日常生活での見落としポイント
皮下脂肪の蓄積・代謝の低下と顎周り脂肪の特徴的動態
皮下脂肪は顎周囲に集中しやすい部位のひとつです。とくに糖質・脂質の過剰摂取や運動不足により全身の代謝が低下し、脂肪が顎下に蓄積しやすくなります。脂肪細胞は年齢とともに減少しにくく、一度蓄えられると解消に時間がかかるのが特徴です。
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 脂肪の付着しやすい部位 | 顎下・頬・腹部 |
| 主な原因 | カロリーオーバー、運動不足、年齢による代謝低下 |
| 栄養摂取との関係 | 高糖質・高脂肪な食事、過度な塩分摂取 |
顎を引いたときに二重顎が現れやすい場合は、脂肪蓄積サインと考えられます。食事内容の見直しや運動の習慣化が不可欠です。
猫背・スマホ姿勢・ストレートネックが顔のたるみに与える影響
現代人に多い猫背や前傾姿勢、ストレートネックは首や顎周囲の筋肉に負担をかけます。正しい姿勢が保てないと筋肉が緩みやすく、フェイスラインのたるみや顎下の皮膚の伸びを助長します。また顎を引いた状態が続くと皮膚や脂肪が下方向へ押し寄せ、二重顎が強調されることも少なくありません。
姿勢の悪化が与える影響を下記にまとめます。
- 首~肩の筋肉の弱化とバランス崩れ
- 顎下リンパの流れ悪化によるむくみ
- ストレートネックによるフェイスラインの変形
- 長時間スマホ操作で顔が前に出たまま固まる習慣
日常的に背筋を伸ばし、スマホやパソコンの高さ・角度を見直すことが不可欠です。
加齢による筋肉・皮膚の変化と生活習慣の接点
年齢を重ねると表情筋や皮膚の弾力が失われやすくなります。特にコラーゲン生成力の低下、筋力低下、外部刺激によって皮膚が下垂しやすくなり、たるみが顎下に現れるのが特徴です。生活習慣によっても進行度合いは異なります。
- 硬いものをあまり噛まない食生活
- 口周りの筋肉を使わない日常動作
- 運動・ストレッチの不足
これらは、加齢と相まってフェイスラインが崩れやすく二重顎の形成につながります。日常生活で表情筋を意識的に動かすトレーニングや、定期的なフェイスマッサージが予防として有効です。
塩分過多・水分過剰摂取が引き起こすむくみのメカニズム
塩分や水分の摂りすぎは体内に余分な水分が滞りやすく、血流・リンパの流れを妨げてむくみを誘発します。顔や顎下のむくみが定着すると一時的に二重顎が目立ち、慢性化すれば皮膚や脂肪のたるみが生じるため注意が必要です。
| 原因 | むくみへの影響 | 対策 |
|---|---|---|
| 塩分過多 | 細胞に水分貯留 | 減塩・カリウム摂取 |
| 水分の摂りすぎ | 排出機能低下 | 適度な水分補給・適度な運動 |
| 運動不足 | リンパ循環鈍化 | 軽い運動・フェイストレーニング |
むくみ予防は塩分管理・適度な水分補給・血流促進の3点がカギです。顔や顎下にむくみを感じたら、すぐに生活習慣を見直すことが重要です。
顎を引くと二重顎になる人の特徴と専門的セルフチェック法
骨格の特徴と歯並び・噛み合わせの二重顎への影響
顎を引くと二重顎になりやすい人には、いくつか共通した骨格的特徴があります。特に、顎が小さい・下顎が後退していると、首から顎にかけての距離が短くなり、皮膚や脂肪がたるみやすくなります。さらに、歯並びや噛み合わせの乱れも顔まわりの筋肉バランスに影響し、輪郭がぼやけやすくなります。
下記のテーブルでポイントを整理します。
| 特徴 | 二重顎リスク |
|---|---|
| 顎が小さい | 高い |
| 下顎が奥に引っ込んでいる | 高い |
| 歯並びの悪さ | 高い |
| 噛み合わせのズレ | 高い |
姿勢や表情筋への影響だけでなく、骨密度の低下や加齢による骨格変化も要因となりやすいので、自分の顎や輪郭の構造を意識してケアを始めることが重要です。
ストレートネックのセルフチェック法と姿勢診断ポイント
ストレートネックは現代人にとても多く、スマホやPC作業の習慣で首の自然なカーブが失われがちです。これが二重顎を誘発する大きな理由になります。以下のチェックステップで自身の姿勢を確認しましょう。
- 壁に背をつけて立ち、後頭部・肩甲骨・お尻・かかとが壁につくか確認する
- 顎を軽く引き自然な頭の位置を意識する
- チンタック(首を後ろへ引く動き)とネックロール(首をゆっくり回す)で可動域や突っ張り感を観察する
- 鏡で横顔をチェックし、頭が肩より前に大きく出ていないか確認する
壁と後頭部の間にこぶし1つ以上空く場合や、首の付け根が前方へ突き出ている場合は、ストレートネックの傾向が強いと言えます。
正しい姿勢は二重顎予防の大前提です。意識して首肩まわりのストレッチや正しい座り方を実践しましょう。
筋力の低下サインと生活シーンでの見分け方
フェイスラインや顎下の筋力低下により、顎を引いた際に脂肪や皮膚がたるみ、二重顎が目立ちやすくなります。自身でできるチェックポイントは以下の通りです。
- 太っていないのに顎下だけたるんでいる
- 硬い食べ物をあまり噛まない食生活
- 長時間同じ姿勢、表情をあまり動かさない習慣
- 「いー」と口を開けた時や顎を持ち上げた時に下顎にうっすら溝や影ができる
下記のリストも参考にしてみてください。
- 顎を引いた時に首と顎の境目がぼやっとする
- 口周りや首の皮膚が動かしにくく感じる
- 鏡や写真で以前よりフェイスラインがもたついている
筋力低下が進行すると、表情筋だけでなく首まわりの筋肉全体のハリも失われ、顔印象が大きく変わります。毎日の生活で顔全体の筋肉をバランスよく使うことが二重顎予防には欠かせません。
今すぐできる!二重顎を防ぐ・改善する自宅エクササイズ・ケア法
顎を引く正しいやり方と癖を直す具体的トレーニング
顎を引く動作は、美しいフェイスラインや小顔効果を目指すために重要ですが、正しいやり方で実践しないと逆に二重顎を引き起こす場合があります。まず意識したいのは、無理に顎を引きすぎるのではなく、首の付け根からゆるやかに引く感覚を持つことです。鏡の前で背筋を伸ばし、目線をまっすぐ前に向け、耳の穴と肩の位置が一直線になる意識を持ちましょう。
おすすめのトレーニングとしては、以下の手順が効果的です。
- 椅子に腰かけ、背中をまっすぐにする
- 顎をゆっくり後方に引いて、二重顎ができるギリギリで止める
- その姿勢を5秒間キープし、これを10回繰り返す
この簡単な習慣を1日に3セット続けることで、正しい顎の位置の癖付けが期待できます。
顎周り・首・口まわりの筋肉を鍛える具体的運動メニュー
二重顎の主な原因は顎下の筋肉(舌骨筋、広頚筋)の衰えや脂肪の蓄積です。効果的な運動を実践することで、フェイスラインの引き締めとリフトアップが図れます。
以下の運動をぜひ日々のケアに取り入れてください。
| 運動名 | ポイント | 回数 |
|---|---|---|
| 舌上げエクササイズ | 舌を上あごに押し付けて5秒キープ | 10回 |
| 口角リフトトレーニング | 口角を思いきり横&上に引き上げて笑顔 | 10回 |
| 首ストレッチ | 首をゆっくり後ろに倒し持ち上げたまま5秒間 | 5回 |
これらは筋肉を効率的に刺激し、血行やリンパの流れの促進にも役立つため、もったりした二重顎の予防・解消に大きな働きをします。
日常生活で意識すべき姿勢と小顔効果を高める癖づけ
日々の生活の中で姿勢や動きを工夫することが、二重顎の根本改善につながります。特にスマートフォンやパソコンの長時間使用によるストレートネックや、前傾姿勢に注意しましょう。
意識すべきポイントをリスト化します。
- スマホやPC作業時は、画面を目の高さに合わせる
- 椅子に浅く座らず、背もたれを使って背筋を伸ばす
- 歩行時や立ち姿勢では頭が前に出ないよう注意する
- 硬めの食品をしっかり噛む食生活を心がける
- 定期的に首と肩のストレッチを行う
これらの姿勢改善と筋肉刺激の習慣を生活に組み込むことで、顎を引いたときでも二重顎ができにくくなり、すっきりとしたフェイスラインを維持しやすくなります。
美容医療での二重顎治療:治療方法・効果・注意点ガイド
メスを使わない施術(ハイフ、脂肪溶解注射など)の特徴と適応例
非外科的な二重顎治療は、ダウンタイムの少なさや負担の軽さが魅力です。代表的なメスを使わない方法には、ハイフや脂肪溶解注射、ラジオ波、リフトアップ専用マシンなどがあります。ハイフは高密度超音波で皮膚奥に熱を与えてフェイスラインを引き締める方法で、肌のたるみや軽度の脂肪に効果的です。脂肪溶解注射は脂肪細胞そのものを分解し、運動や食事で落ちない部分痩せに適応します。
それぞれの施術ごとの特徴を下記にまとめます。
| 施術名 | 効果 | リスク・副作用 | 治療期間 | 適応例 |
|---|---|---|---|---|
| ハイフ | 引き締め・たるみ改善 | 赤み・腫れ | 1回〜数回 | 軽度のたるみ、予防ケア |
| 脂肪溶解注射 | 部分痩せ | 痛み・腫れ | 2〜4週間間隔で数回 | 局所的な脂肪、比較的若年層 |
| ラジオ波 | 引き締め・代謝促進 | ほてり・赤み | 数週間に1回 | 軽度のたるみ、全体的なケア |
| リフトアップ機器 | 引き上げ・肌質改善 | 一時的な違和感 | 1〜2か月間隔 | フェイスラインのゆるみ予防 |
副作用として腫れや赤み、まれに軽い痛みが生じることもありますが、基本的に数日以内には治まります。リスクが少なく、忙しい方や初めて美容医療を受ける方にも適した選択肢です。
外科的施術(脂肪吸引、糸リフトなど)による即効的改善法
即効性を重視したい場合や、目に見えてはっきりした変化を求める方には外科的施術が選ばれています。中でも脂肪吸引や糸リフトは二重顎治療で非常に人気があります。脂肪吸引は皮下脂肪を直接除去するため、一度の施術でしっかりとした効果が実感でき、リバウンドも少ないです。糸リフトは皮膚の下に特殊な糸を挿入し、たるみを物理的に引き上げ、フェイスラインを整えます。
外科的施術のポイントをまとめます。
| 施術名 | 方法 | 効果持続性 | 回復・ダウンタイム | 費用感(目安) |
|---|---|---|---|---|
| 脂肪吸引 | 小切開からカニューレで脂肪吸引 | 半永久的 | 1週間前後 | 20万円〜40万円 |
| 糸リフト | 溶ける糸/特殊な糸でたるみを引き上げる | 1〜2年 | 数日〜1週間 | 10万円〜30万円 |
いずれも施術後は腫れや内出血が出る場合もあります。施術の効果は持続期間が長いため、根本からの解決が可能です。費用は施術内容や部位、クリニックによって異なりますが、いずれも安価ではないため十分なカウンセリングが必須です。
患者の体験談やモニター募集情報の紹介
治療選択時には、実際に施術を受けた方の体験談や口コミが参考になります。多くの方が「ハイフで短期間で引き締まりを体感した」「脂肪吸引で長年の悩みから解放された」など満足度の高い声を寄せています。特に回復期間・痛み・仕上がりの違いに関する実感値がリアルに記されており、施術を選ぶ上で安心材料になります。
また、多くの美容クリニックでは新メニュー導入時や症例拡大のためにモニター募集があります。モニター制度は通常よりも安い費用で受けられ、術後の経過写真や体験アンケートの提出を条件にするケースが大半です。
体験者のリアルな意見やモニター情報を積極的にチェックすることで、自分に合った施術方法をより具体的にイメージでき、納得して治療を選択しやすくなります。
子供や痩せ型でも起こる二重顎の医学的原因と対策
骨格発育と筋肉衰弱が招く若年層の二重顎事情
子供や痩せている人でも二重顎が目立つ理由は、骨格や筋肉に関係があります。顎が小さいと、脂肪が少なくても皮膚や筋肉のたるみが強調されやすくなります。成長期は顎や骨格がまだ発達途中であり、長時間スマホを見るなどの悪い姿勢が続くと、首や顎周りの筋肉が十分に鍛えられず、フェイスラインのもたつきやたるみが生じやすくなります。
下記の表に、主な医学的原因をまとめます。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 骨格の特徴 | 顎が小さい・後退していると二重顎が目立つ |
| 筋肉の衰え | 首や顎周りの筋肉使用が減るとたるみやすい |
| 姿勢の乱れ | 猫背やストレートネックで脂肪や皮膚が寄る |
| 歯列・かみ合わせ | 噛む力が不足すると筋力低下の原因に |
早期からの正しい姿勢や筋肉の使い方を意識することが、美しいフェイスライン作りに直結します。
生活習慣と姿勢の早期改善で予防できるポイント
生活習慣の改善は二重顎予防に直結します。特にスマートフォン、ゲーム、読書などでうつむき姿勢が習慣化すると、首の筋肉が緩み、あごのラインが崩れやすくなります。また、やわらかい食事ばかりだと咀嚼筋が十分に働かなくなり、筋肉低下を招く要因となります。
予防のためのポイント
- 顎を自然な位置で保つことを意識する
- 読書やスマホは目線の高さで使い、長時間うつむかない
- 食事では硬い食材を積極的に取り入れて咀嚼回数を増やす
- 親子で首や顔のストレッチ、簡単な表情筋トレーニングを行う
- 姿勢矯正クッションやストレッチポールの活用
日々の生活でこれらを意識的に取り組むことで、顎や首周りの筋肉を鍛え、二重顎リスクを軽減する効果が見込めます。特に成長期や体型にかかわらず、姿勢と筋力バランスを整えることが大切です。
関連する病気リスク(顎関節症、睡眠時無呼吸症候群)と注意
二重顎の陰には重大な病気が潜んでいることがあります。顎関節症は顎や顔の筋肉を動かすのが難しくなり、筋肉の衰えやむくみの原因となります。また、首周りの筋肉が緩むことで睡眠時無呼吸症候群を引き起こすことがあり、夜間の呼吸が浅くなって集中力低下や慢性的な疲労感の原因となることも指摘されています。
注意するべき症状リスト
- 顎を動かすと痛みや違和感がある
- 寝ているといびきや無呼吸が指摘される
- 朝起きたとき顔や首がむくむ
- 顎や首にしこり・ふくらみがある
これらの症状が見られる場合は、医師の診察を受けることが重要です。健康的なフェイスラインを保つためには、日々のセルフチェックも忘れずに行いましょう。
撮影時に必須!二重顎を防ぐ写真映えポージング&表情テクニック
顎を引かずに小顔に見せるポージングのコツ
写真で二重顎を目立たせないためには、顎の位置と首のラインを意識することが重要です。顎を引きすぎるとフェイスラインの脂肪や皮膚が押し上げられ、二重顎が強調されるため注意が必要です。
以下のテーブルでは、実践しやすい小顔ポージングのポイントを紹介します。
| ポージングテクニック | 効果 | ワンポイント |
|---|---|---|
| 顎をほんの少し前に出す | フェイスラインがすっきり出る | 首筋を伸ばす感覚で |
| 首を長く見せる | たるみを目立ちにくくする | 背筋を伸ばす |
| カメラから気持ち下を向く | 顔の立体感が強調される | 目線はレンズ上 |
強調ポイント
- 顎を軽く突き出すことで顔全体の影が少なくなり、小顔効果が生まれます
- 自然な笑顔を保つことで緊張感や不自然な筋肉のたるみを防げます
- 姿勢を正して首回りを意識すると写真映えにも直結します
日常から「顎を引く癖」や「ストレートネック」になりやすい姿勢には注意し、首・顎の自然なラインを意識しましょう。
簡単にできる表情筋トレーニングと笑顔のつくり方
二重顎対策として日々の表情筋トレーニングは非常に有効です。フェイスラインの筋肉を鍛えることで、脂肪やたるみの予防につながります。以下のトレーニングを取り入れることで、自然で立体的な笑顔と理想のフェイスラインを目指せます。
- あいうえお体操
大きく口を開いて「あ・い・う・え・お」と発声し、表情筋全体を動かします。 - 舌回し運動
口を閉じて舌先で歯茎の周りをゆっくり10回まわす。右回り・左回りをそれぞれ実施。 - 顎持ち上げストレッチ
上を向き、天井を見ながら5秒キープ。その際首の前側を意識すると筋肉が刺激されます。
ポイント
- 朝晩2回、継続することで効果実感
- 口角を上げる意識を持ち自然な笑顔に繋げる
トレーニングを日課にし、筋力低下や表情のこわばりを予防しましょう。
写真補正アプリやグッズの活用法の現実的効果と注意点
写真撮影時に二重顎が気になる場合、近年は手軽に使用できる写真補正アプリや、リフトアップテープなどのグッズを活用している方も増えています。それぞれのポイントと注意点を比較表でまとめます。
| 方法 | メリット | 注意点 |
|---|---|---|
| 写真補正アプリ | 即時で手軽に修正可能 | 加工過多は不自然さや違和感が出やすい |
| リフトアップテープ | 肌のたるみを持ち上げ | 長時間の使用は肌トラブルの原因になる |
| フェイスバンド | リフト効果が感じやすい | 毎日使用は血行不良に繋がることも |
活用の際の注意
- アプリ任せではなく根本改善も、同時に目指す姿勢が大切
- 過度な物理的対策は肌や表情筋の負担に注意
- SNS用の加工写真と実際の見た目を一致させる意識で自信を持ちましょう
二重顎の根本的な解消・予防には、日々のケアや生活習慣の見直しも欠かせません。写真映えを意識しつつ、健康的で自然な美しさを目指しましょう。
専門データと最新知見で紐解く二重顎の実態と男女年齢別比較
国内外の統計データからみる二重顎の発生状況と原因分析
厚生労働省の調査や海外の皮膚科学会報告によると、二重顎は年齢や性別、生活習慣により発生率が異なります。国内の20~40代女性では、全体の約36%が「写真で二重顎が気になる」と回答しています。特にスマートフォンの長時間使用などによるストレートネックの増加が、この現象を促進しています。
性別では男性より女性に悩む人が多く見られ、原因は単なる脂肪蓄積だけでなく、加齢による皮膚のたるみや筋肉の衰え、骨格の違いが挙げられます。痩せ型でも「顎が小さい」「噛む回数が少ない」ことで筋肉が弱くなり、皮膚や脂肪が押し出されやすくなることも明らかになっています。さらに年齢別で見ると30代後半以降で発生率が上昇し、早期の生活習慣改善が大切です。
| 年代 | 男性発生率 | 女性発生率 | 主な要因 |
|---|---|---|---|
| 20代 | 8% | 15% | 骨格・遺伝・姿勢 |
| 30代 | 13% | 22% | 筋力低下・皮下脂肪増加 |
| 40代 | 17% | 29% | 加齢・皮膚や筋肉のたるみ |
| 50代 | 20% | 33% | 老化・ホルモンバランスの変化 |
二重顎の発生には様々な関連因子が考えられ、生活習慣や遺伝・姿勢が複雑に絡み合っていることがデータから読み取れます。
専門家の意見・医学的知見の最新まとめ
医療専門家によると、「顎を引くと二重顎になる」現象には主に以下の要素が組み合わさっています。
- 長時間のデスクワークやスマートフォン使用によるストレートネック
- 顎下や首まわりの皮下脂肪の蓄積およびリンパの流れの悪化
- 咬筋や舌骨筋群など顔・首の筋肉の衰え
- もともと顎が小さい骨格や遺伝的要素
正しい対策法として推奨されるポイント
- 頭の位置を意識し、背筋を伸ばした自然な姿勢を保つ
- あご周りの筋肉を鍛えるトレーニングやストレッチを日常的に行う
- 噛みごたえのある食品を意識的に取り入れ、筋肉使用を増やす
- 適切な水分補給でリンパや血流の流れを改善
こうしたセルフケアを継続することで、写真や普段の生活で顎を引いても二重顎が目立ちにくいすっきりしたフェイスラインを保ちやすくなります。医師の見解では、症状が進行していたり加齢的な要素が強い場合は美容外科や皮膚科などでの専門治療を検討するのも有効です。
セルフチェックとしては、水平姿勢で口角横の皮膚を軽くつまんだときの厚みや、顎下にしわや膨らみがどれだけ現れるかを観察する方法が手軽で推奨されています。発生原因に合わせ、生活スタイルの見直しやトレーニングで早期改善を図ることが大切です。